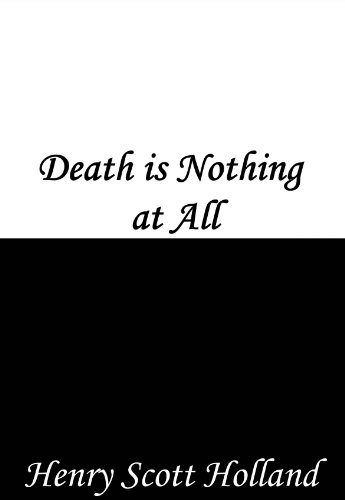大学時代の1年下の後輩、H君が亡くなった。
享年41歳、死因は脳炎だそうだ。
H君はベーシストだった。
高校まではエレベを弾いていたが大学からジャズをやりたくなって軽音楽部に入り、わたしはそこで彼と出会った。トランペットを吹いていたわたしは、セッションなどで演奏する機会が多そうなものだが、考えてみるときちんと一緒にやったバンドは一つしかなかったように思う。そのバンドでも、練習ではわたしは上からああだこうだ言うことが多く、実は一緒に音を出した瞬間は短かったのかもしれない。
わたしの学年には優秀なベーシストがいて、必然的に彼とやる機会の方が多かったし、やりたい気持ちが大きかった。H君の学年はわたしの学年と比べると部員やマニアックなジャズ好きが少なくて、H君にとっては音楽的欲求が満たされなかったかもしれない。そのくせ、学年を超えてバンドを組むことが少なかった。「あんたらは自分たちだけでつるまないで、オレ達もかまってくれよ!」 H君ではないけど、そんなことを言われたこともあった。その場にH君がいたかどうかは覚えてないが、H君も同じ気持ちを抱いていたかもしれない。はにかむような苦笑いが目に浮かぶ。ごめんね。でも、こっちも余裕なかったんだよ。これは後悔してる。
H君は「いい奴」だった。
器用なタイプではなかったかもしれない。だが、真面目で練習熱心で、先輩風を吹かせた酒の席にもよく付き合ってくれた。考えてみれば、わたしの最低な下ネタによく我慢してくれたものだ。そういえば、あるとき『Word of Mouth』は人生で3本の指に入るくらい好きなんだ、と言ったら、あれはいいですよね、と同意してくれた。でも、本当はジャコよりマーカスの方が好きだったんじゃないかと思う。4ビートならスコット・ラファロやポール・チェンバースよりもジミー・ギャリソン。そしてエリントンオケなら、ジミー・ブラントンよりもアーニー・シェパード。H君の音楽性からすると、それが好みだったはずだ。
そして、そんな彼の人柄のせいだろう、彼は部で人をまとめる役職に就いた。
適任だと思った。
その就任を聞いて誇りに感じたし、実際、彼の働きも周囲の期待を裏切らないものだった。男に好かれる、信頼される男とでもいえばいいのか、彼には人望があった。誘えば断らない、でも、自分の嫌なことははっきり嫌だと言えること。そして自分の核となる信念は曲げない、そんなところがあった。
H君は成長した。
わたしはH君と音楽的に深い付き合いはできなかったが、それはわたしの同学年の友人が解消してくれた。
わたしが学部を卒業した後の院生時代に早々と自分勝手な理由で現場から遠ざかったわたしを、その友人は自分のバンドのライブに誘ってくれた。場所は京都のParker House Roll だったはず。初夏だったか初秋だったかで、少しだけ暑さを感じる季節だったことを覚えている。
そのライブはとてもよかった。
4ビートを基調に、しかしコンテンポラリーなジャズをやることをコンセプトにしたバンドで、ちゃんとバンド・サウンドになっていた。メンバーはわたしのよく知る友人や後輩で、正直、その演奏に嫉妬してしまった。悔しかったから、一言も正直な感想は言わなかった/言えなかったし、そのときのわたしには言う資格もなかった。
今だって、「まあ、MCはオレの方が上手いけどね」と憎まれ口を叩くのが精一杯だ。
そして、そのライブのH君はとても輝いていた。
4ビートに安定感があり、バンドが彼を信頼していることが感じられた。ベースソロは少しせせこましく感じたけど、それは彼の持ち味だ。今でもありありと思い出せるのは「チュニジアの夜」。その友人の趣味なのか、アレンジは人力ドラムンベース。
シンセベースを真似たH君のウッドベース。
あれはよかった。エレベをやっていた君のキャリアが活きてたね。たしかその頃だ、この友人は、「同じ年代の中では、Hが一番いい4ビート弾くようになったなあ」と言っていた。いや、4ビートだけじゃないよ。ウッドベースとの距離がいきなり縮まったんじゃないのかな。とにかく、あのときは嬉しかったんだ、H君の成長が感じられて。
H君のその後は、断片的にしか耳にしていない。
それも、専ら音楽以外のことだけです。
所属している研究室? が画期的な成果を上げてブレイクしてることを口伝え(word of mouth)で聞いた。そして、その後に重い病気に倒れて、日常生活を送ることが難しくなったらしい、ということとか。
仕事とプライベートの関係で、わたしはようやく身軽に動けるようになったところ。
ここ数年は昔からの友人・知人との旧交を温めているところだった。
そのリストにH君の名前も挙がっていたが、これは無理になってしまった。
「だった」「あった」「輝いていた」と、この文章を、過去形で書かなくてはいけないことがどうしようもなく辛い。
亡くなった人間のために、残された人ができることは何も無い。
ただ、その人のことを忘れず、その思い出、その人への思いとともに、一緒に生きていくこと。
それが一番の供養・追悼なのだとわたしは考えています。
H君、闘病生活がんばったね。お疲れさま。
短い間だったけど、一緒に共有できた時間は楽しく、うれしかった。
その魂の安からんことを。