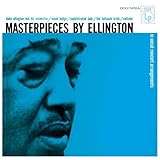前回に引き続き、小川隆夫氏の著作から。
前回は、第1次大戦終了後の「ハーレム・ルネッサンス」におけるエリントンについてこの本が取り上げている個所を引いた。
今回はレコード・メディアとエリントンの関係についてみてみることにする。
現代の人間がエリントンを聴くとき、常に意識しておくべきことがある。それは、エリントンの音楽的なキャリアは50年に及び、その作品はすべてレコードで発表された、ということだ。ここまではすぐに想像がつく常識の範囲内の話だが、重要なのはさらにこのレコードの時代は大きく2つに分けられるということ。すなわち、LPとSP。
レコード・コレクターにとっては常識、しかし一般的な人には未知の世界。というかどうでもいい話かもしれない。今回はそんな話だ。
はじめに
なお、あらかじめお断りをしておきたいことがある。LPが世に登場するのは五〇年代に入ってからだ。それまではSPと呼ばれる、片面に一曲しか収録できないシングル盤が一般的だった。本書(とくに第一章)ではLPが登場する以前の演奏や作品についても触れているが、それらはコンピレーションと呼ばれるオムニバス盤に収録されたものだ。
エリントンに限らず、50年以前の音源を聴く難しさはここにある。当時、1枚の音源は文字通り「アルバム」であって、ヒット作の寄せ集めでしかない。現代のような1つのコンセプトの下に複数の曲を創りあげ、ある世界を提示する、という考えはない。さらにいうなら、「音源を購入し、個人的な範囲の使用目的で鑑賞する」 という、現代に生きるわれわれが当然のこととして行っている音楽の楽しみ方のスタイルも、ごく最近に確立された一時的なものでしか無い(そのことは、音源のダウンロード販売が市民権を得てきていることからも明らかだ)。当時、音楽は街のジューク・ボックスで1曲いくらで聴いたり、やラジオから流れるものであって、レコードを収集して家でこっそり聞いて楽しむものではなかった。
古い時代の音楽を聴くときは、その次代の時代背景、メディアの環境も考慮すると、その音楽のことについてもっと多くのことがわかる。これ以上うるさいことを言うつもりはないが、これは事実だ。
だが、先を急ごう。今日はメディアの変遷の話だ。
LPが登場
ジャズには《三分間芸術》という言葉がある。現在のCDが登場する前は、シングル盤やLP盤と呼ばれるレコードが音楽を記録する媒体として一番ポピュラーなものだった。ただし、最初からLPが存在していたわけではない。当初はSP盤と呼ばれるフォーマットが用いられていた。これは1分間に78回転するレコードのことで、直径10インチと12インチの盤があり、前者で3分、後者で5分前後の演奏が収録できた。ジャズでは10インチ盤が主流だったことから、≪三分間芸術》と呼ばれたのである。ちなみにSPはStandard Play、LPはLong Playを略したものだ。
画期的な技術革新がLP誕生の背景にはある。ひとつはディスクの素材が粒子の粗い合成樹脂のシェラックからポリ塩化ヴィニールの化合物(PVC)に代わったこと。SP盤には割れやすい弱点があった。それがPVCの使用によって、落としても割れない丈夫なものに変身したのである。
PVCの登場は、およそ50年におよぶ78回転ディスクのありかたを根底から覆すことにつながった。素材が壊れやすいので、シェラックの場合は一センチあたりで盤に溝が40ほどしか彫れない。それが頑丈なPVCを使用すると、溝が100あまりになった。そのうえ、回転数を落としても音質の劣化が認められない。
物理特性を考えれば、SP盤より音質がいいほどだ。回転数は半分以下の33回転になり、溝の数は2.5倍になった。これで、同じ10インチでも約5倍に収録時間が延長される。
録音方式の進歩もLPの開発に拍車をかけた。それまでのレコーディングは、ラッカー盤と呼ばれるディスクに直接溝を彫って音を記録するのが一般的だった。それが30年代後半になると、磁気テープを用いた録音方式の実用化に向けてさまざまな試行錯誤が繰り返されるようになってくる。当初は紙テープに磁気を塗って録音するタイプだったが(『ミントン・ハウスのチャーリー・クリスチャン』がこの方式で録音されている)、これだとテープがすぐに切れてしまう。そこで使用されるようになったのがヴィニール製のテープだ。
1947年には、アンペックス社が初めてスタジオ用テープ・レコーダーを完成させている。それを受けて、翌年からコロムビアとビクターが磁気テープ録音を全面的に採用することにした。軽くてコンパクト、保存に便利で音質も安定していることから、テープ録音が急速に普及する。
PVCとテープ録音の両方を採用した最初のレコード会社はコロムビアだ。同社はその方式を用いたLPを48年に発売したが、これは長時間の演奏が当たり前のクラシック用としてだった。
そして、49年にはダイアルが『チャーリー・パーカー/ザ・バード・ブローズ・ザ・ブルース』を、翌年にはサヴォイがこれまたパーカ―の『ザ・チャーリー・パーカー・クインテットVol.1』をリリースし、メジャー・レーベルのコロムビアもデューク・エリントン楽団の『マスターピーセズ』を出したことから、ジャズの世界に10インチLPの時代が到来する。 (49-51頁。なお、原文の漢数字は算用数字に改めた)
簡潔にして必要な情報は揃っている。小川隆夫氏はこういう説明をきちんとしてくれるからありがたい。でも、ごめんなさい・・・ エリントンファンからのつまらない指摘をひとつだけ。小川氏が写真付きで挙げてくれているエリントンの『Masterpieces by Ellington』のジャケット、これは56年の再発盤です!
51年の初回盤は50年代の香り漂うこっちのジャケット。
まあ、再発のほうが段違いでシックなんですけどね。ここは 初回盤のジャケットを掲載してほしかった。。。この作品は丁寧に聴きこむに値する、タイトル通り「傑作」なのだが、詳細はまたエントリを改めて書く。簡単にエリントンの状況を述べると、年代区分でいうと46年の『Black, Brown and Beige』の上演以後、エリントンは大いなる実験の時代に突入する。この時代はゆったりとしたグルーヴの中、ブルージーでありながら優美なサウンドが特徴的な時代で、この作品でも、15分を超える「Mood Indigo」などはその実験精神がモロに表れた演奏だ。本作品の後、「ホッジスの乱」によって大きなメンバーチェンジを余儀なくされ、エリントンは引き続き自分の求めるサウンドを追求することとなるのであった。
さて、再発盤でグッと手に取りやすくなったものといえば、こんなのもある。
初回盤。
『The Duke Plays Ellington』(capitol, 53年)

再発盤。
『Piano Reflections』(72年)

現在入手しやすいCDは紫色。エレガントです。
何かの話のタネになるかもしれないので、パーカーの方もジャケットだけ挙げておく。
『Bird Blows the Blues』(dial, 50年)


チャーリー・パーカー・ストーリー・オン・ダイアル Vol.1
- アーティスト: チャーリー・パーカー
- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック
- 発売日: 2016/10/26
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
いま気づいたことだけど、メシオのこのCD、もしかして「ダイアルのパーカー」を意識していたのだろうか。どちらも「パーカー」なだけに。

- アーティスト: メイシオ・パーカー
- 出版社/メーカー: ビクターエンタテインメント
- 発売日: 2000/03/23
- メディア: CD
- 購入: 2人 クリック: 7回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
そういえば、LPが登場した当時、一般的にはジャズをLPで発売することは受け入れられなかったらしい。ただ、これは何か具体的な否定の根拠があったというよりは、そもそも「ジャズを長い時間聴く」という発想がなかったからだと思われる。
そんなジャズとレコードの関係について、以前にざっと読んだ本がこれ。エリントンを聴くにあたり、もう一度(と言わず何度でも)読み直すことの必要性を強く感じている。
以前にこの本を読んだとき、ものすごく勉強になったことを覚えている。俺はこんなことも知らずにエリントン、エリントンと言っていったのか・・・とショックを受けたような。「音楽を楽しむのに多すぎる知識はいらない。1番大事なのは音楽を感じる感性だ」 というナイーブな意見も真実ではあるけれど、その反面、60年以上も昔の文化をいきなり聴いて感じ取れるのか、という考えもあると思う。管理人は、いろいろな知識があればその分だけ音楽を深く楽しむことが考えている。その面から言うと、この本は実に面白かった。
ただ、この本いい本だと思うけど、あまり読まれてないのかなあ。翻訳のタイトルが少しおっかなく感じてしまうのかもしれない。なにしろ「全歴史」とあるから、少し身構えてしまう。原題は "Jazz On Record : A History" だから、もう少し軽いニュアンスなのでは。
さて、今回はどうもうんちくというかマニアックな知識の話で、「勉強」なんて言葉まで出てしまった。ジャズ(とエリントン)はもっと自由に聴かれてほしい、とは思うけど、深く楽しもうと思うと、どうしてもある程度は知識は必要になってくる。そのあたりを、せめてエリントンに関するところだけでもコンパクトにまとめられたら、とも思っている。
参考までに、ジャズ・レーベルに関する本はこんなものがある。
ただし、この「増補版」はあまり評判がよくない。
「増補版」というよりも「第2版」とか「改訂」くらいでよかったのでは、とのこと。
マニアックなところではこんな本も。
この本こそ、そろそろ「第2版」がほしいところです。